証券会社の活動
- 企業の株式発行を取り扱う
- 株式の売買を仲介して手数料を得ている
保険会社の活動
- 生命保険や損害保険などの加入者から掛金(保険料)を受け取る
- 死亡、火災、自動車事故などが発生したときに保険金を支払う
- 掛金の受け取りと保険金支払いまでの間に、顧客から積み立てられた準備金を使って利益を得る
- 企業に融資して利子を得る
- 不動産、国債、株式などに投資して利益を得る
証券会社の活動
保険会社の活動
銀行の活動
預金の種類
貸出の種類
銀行の信用創造
金融機関とは
金融機関の種類
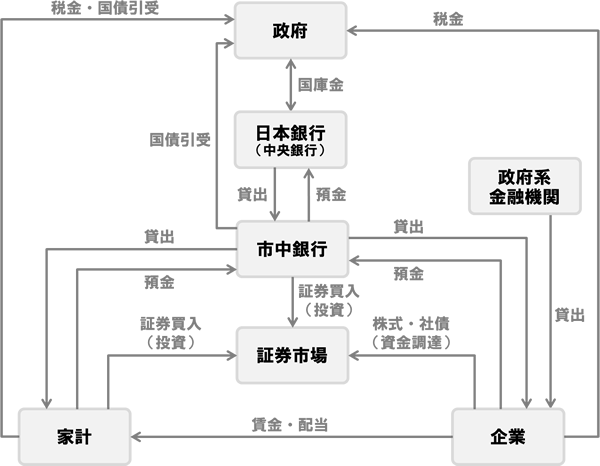
金融
間接金融
間接金融の発展
貨幣=経済活動の血液
経済と貨幣の関係
通貨供給量=マネーサプライ
貨幣の機能
現金通貨と預金通貨
日本の税制
↓
↓
↓
↓
↓
所得税の税率
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円を超え~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円を超え~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円を超え~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円を超え~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円を超え~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
確定申告
国税と地方税
間接税と直接税
日本国憲法における国民の三大義務
租税
公平の原則
累進課税制度
租税法定主義の原則
特例国債(赤字国債)
特別国債の大規模発行における問題
財政構造改革法