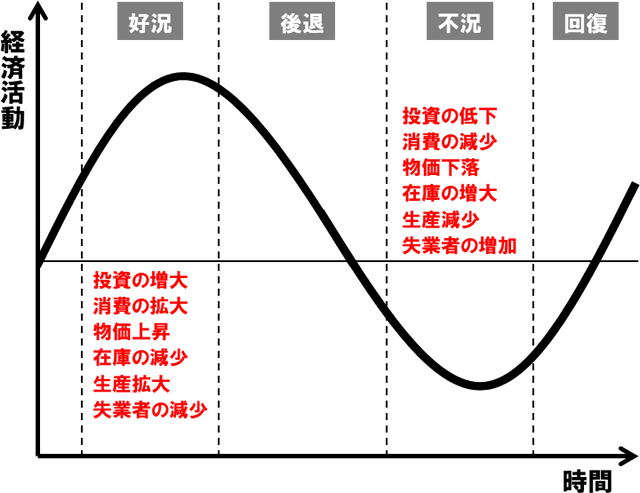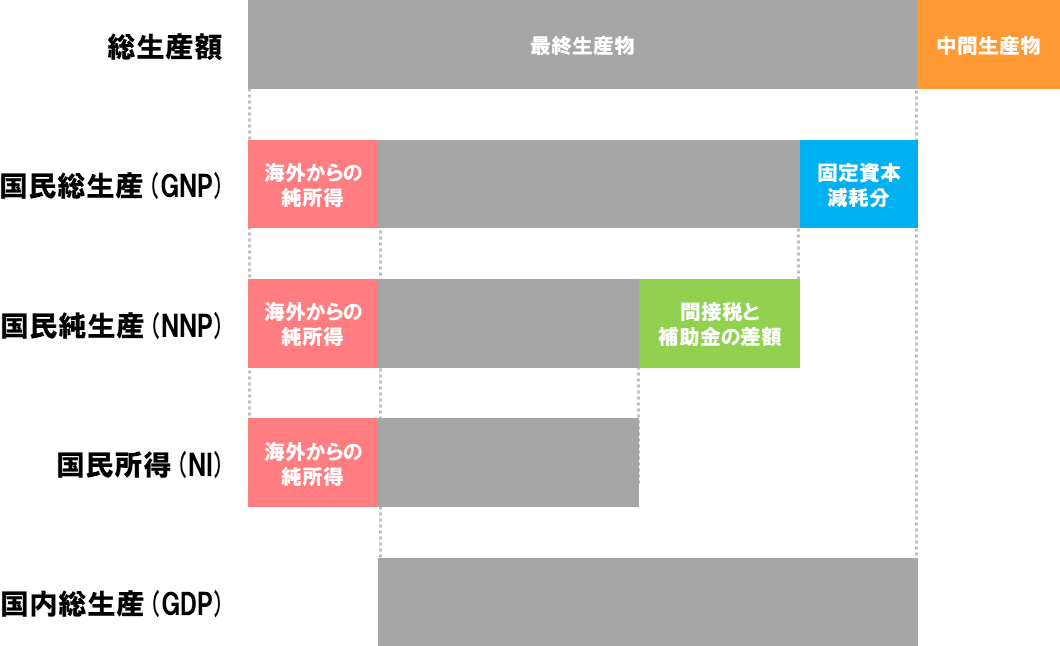国の予算
- 財政活動は、 1年間を会計年度とする予算に基づいて行われる
- 日本では、4月1日から翌年の3月31日までが「一会計年度」である
予算の構成
- 一般会計予算
- 内閣で1年間の歳出と歳入の原案が作成され、国会で承認を受けて執行される(財政民主主義の原則)
- 一般会計には、そのときの経済の状況や経済政策の特色が現れる
- 例)
国債の発行による歳入の増加
国債の利払い、償還のための国債費の割合が増大
社会保障関係費の増加 → 高齢化社会
地方交付税交付金の増加 → 地方格差の解消
公共事業関係費の増加 → 景気対策
- 例)
- 特別会計予算
- 以下のときに限り、財政法のもとで設置することができるもの
- 特定の事業を行なう場合
- 特定の資金を保有してその運用を行う場合
- その他、特定の歳入をもって特定の歳出に充て、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合
- 以下のときに限り、財政法のもとで設置することができるもの
財政投融資計画(第二の予算)
- 重要産業の育成、産業基盤(道路・港湾など)の整備、住宅建設の促進、農林水産業や中小企業の助成を行うための資金
- 財投債や財投機関債・政府保証債を発行して調達したり、簡易保険積立金などを政府関係機関や地方公共団体などに投資や融資して資金を集める
- 財投債に充てられる郵便貯金・厚生年金・国民年金の積立金
- 以前は、旧大蔵省資金運用部を通して投資や融資されていた
- 近年は、各機関が自主的に運用できるようになった
- 公共事業
- 以前は、生産関連社会資本(公園、上下水道、教育施設、病院、道路など)の整備がメインであった
- 近年は、生活関連社会資本の充実や、情報通信分野の成長産業育成のための基盤整備が求められている
- 近年は、公共事業の見直しも行われている
- 環境への影響を事前に調査する「環境アセスメント」の導入
- 不要な公共事業を見直す「時のアセスメント」制度の導入
参考:財務省 – 予算