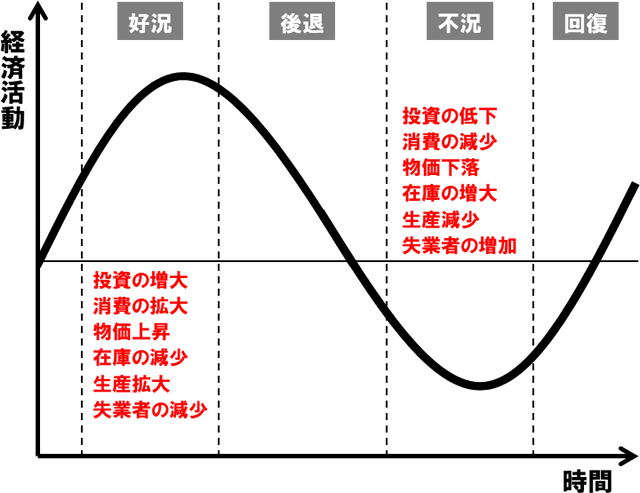日本の税制
- 第二次世界大戦後、1950年のショウプ勧告に基づく税制改革
- シャウプ税制:所得税、法人税、富裕税、相続税といった直接税を中心とし、補完税として酒税、専売益金といった間接税を配する税体系
- 日本はシャウプの税制改革により、所得税を中心とする直接税中心主義をとってきた
↓
- 高度経済成長が終わり、安定成長になると、所得税・法人税などの税収の伸びが鈍ってきた
- 少子高齢社会に向けて新たな財源を考える必要性
↓
- 不公平税制が問題となってきた
- 給料から直接所得税を源泉徴収されるサラリーマンと、自分で所得を税務署へ確定申告する自営業者等とで、税務署が把握する所得の捕捉率に格差がある
- サラリーマンの補足率:9~10割
- 自営業者の補足率:5~6 割
- 農民の補足率:3~4 割
- 税の不公平
- 1トーゴーサン(10・5・3)
- 1クロヨン(9・6・4)
- 給料から直接所得税を源泉徴収されるサラリーマンと、自分で所得を税務署へ確定申告する自営業者等とで、税務署が把握する所得の捕捉率に格差がある
↓
- 1989年、税制改革
- 直接税中心の税制を、間接税の割合が高い税制へ改める動き
- 所得税や法人税の税率が下げられる
- 消費税3%が導入される
↓
- 1997年、消費税が5%に引き上げられる
- 消費税のうち1%は「地方消費税」として地方税に組み入れられる
↓
- 少子高齢社会の進展
- 若年層の租税負担が増えることが予想される