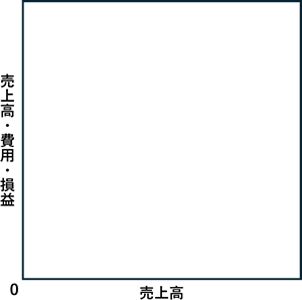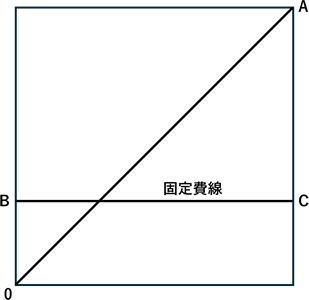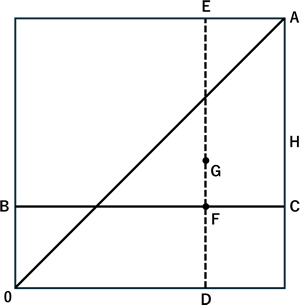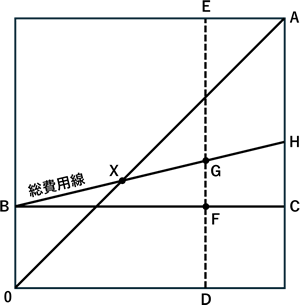日本においては国際会計基準への準拠
- 1990年代後半から2000年代前半に証券取引法の規制対象の上場会社に適用される会計基準の大幅な改正が行われた。
- 国際会計基準に準拠する国内基準の改変は俗に「会計ビッグパン」とも呼ばれる。
制度改革の背景
- 日本企業の国際化や多角化がすすみ、多国籍企業として成長した。
- 国際的に日本の会計基準の不備が指摘されつづけてきた。
- 国際的な資金調達需要の増大によって外国人の投資者が増加した。
- 証券市場がボーダーレス化した。
- 「会計基準のコンバージェンス(会計基準の統一)」が求められてきた。
会計基準の国際比較
| 会計基準 | 項目 | 日本基準 | 国際会計基準(IAS/IFRS) | 米国基準 |
|---|---|---|---|---|
| 金融商品 | 有価証券の評価分類によリ、時価ないし償却原価法(債券) | 分類により、時価ないし償却原価法(債券) | 分類により、時価ないし償却原価法(債券) | 分類により、時価ないし償却原価法(債券) |
| 貸倒見積高の算定/減損の測定 | 割引将来キャッシュフロー | 割引将来キャッシュフロー | 割引将来キャッシュフロー | |
| 金融資産の消滅 | 法的保全の要件あリ(財務構成要素アプローチ) | 法的保全の要件なし(主としてリスク・経済価値アプローチ) | 法的保全の要件あリ(財務構成要素アプローチ) | |
| デリバティブの評価 | 時価 | 時価 | 時価 | |
| ヘッジ会計 | ヘッジ会計の要件を満たす場合 | ヘッジ会計の要件を満たす場合 | ヘッジ会計の要件を満たす場合 | |
| 企業結合 | 基本的方法 | パーチェス法 | パーチェス法 | パーチェス法 |
| 持分プーリング | 法厳格な要件を満たした場合のみ例外的適用 | パーチェス法のみ | パーチェス法のみ | |
| のれん | 厳格に償却及び滅損 | 非償却、減損のみ | 非償却、減損のみ | |
| 資産の減損 | グルーピング | 概ね独立したキャッシュフローを生み出す最小の単位 | 概ね独立したキャッシュフローを生み出す最小の単位 | 概ね独立したキャッシュフローを生み出す最小の単位 |
| 減損の兆候 | 評価する | 評価する | 評価する | |
| 認識テスト | 割引前将来キャッシュフロー | 回収可能頡(正味売却価額と使用価値のいずれか高い方) | 割引前将来キャッシュフロー | |
| 測定回収可能額(正味売却可能額と使用価値のいずれか高い方) | 回収可能額(正味売却可能額と使用価値のいずれか高い方) | 公正価値 | ||
| 減損損失の戻入れ | 戻入れなし | 戻入れあリ(のれんを除く) | 戻入れなし | |
| 退職給付 | 負債の計上 | 退職給付債務に未認識の過去勤務債務及び数理計算上の差異を加減し、年金資産を控除した額 | 退職給付債務に未認識の過去勤務債務及び数理計算上の差異を加減し、年金資産を控除した額 | 退職給付債務に未認識の過去勤務債務及び数理計算上の差異を加減し、年金資産を控除した額 |
| 数理計算上の差異 | 厳格に全領償却対象 | 回廊超過分を償却 | 回廊超過分を償却 | |
| 最小負債の計上 | なし | なし | 未積立累積給付債務を計上 | |
| 税効果 | 基本的方法 | 資産負債法 | 資産負債法 | 資産負債法 |
| 繰延税金資産の計上 | 回収可能性/実現可能性による | 回収可能性/実現可能性による | 回収可能性/実現可能性による | |
| リース | ファイナンスリースの処理 | 資産または費用 | 資産 | 資産 |
| 研究開発費 | 開発費の処理 | 費用 | 資産 | 費用 |
| 連結財務諸表 | 子会社の範囲 | 支配力基準 | 支配力基準 | 持株基準 |
| 投資不動産 | 測定 | 原価 | 公正価値ないし原価 | 一般的に原価 |