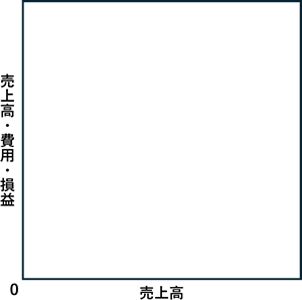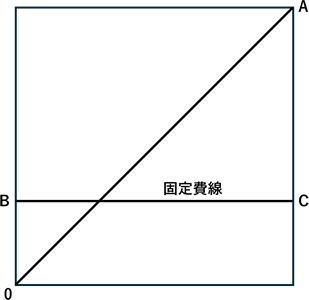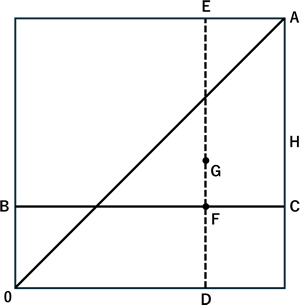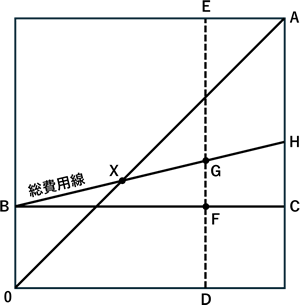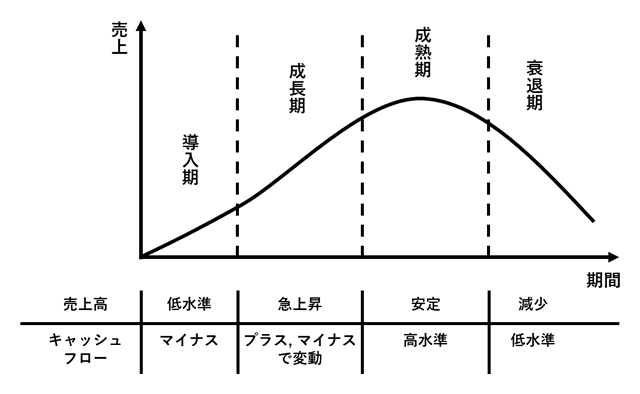トライアングル体制
- 日本においては系統の異なる3つの法律が会計という行為を規制し、独特のバランスを保っていたが、現在で各法律が歩み寄ってきている。
- 会社法(かつての商法)
- 金融商品取引法(かつての証券取引法)
- 税法(法人税法)
- 会社法、金融商品取引法、税法という法制度の枠内で行われる会計、または法律の目的を果たすために行われる会計
- 会社法会計
- 金融商品取引法会計
- 税法会計
企業会計基準
- 企業会計基準
- 会社法会計、金融商品取引法会計、税法会計のより所となる存在
- いかなる企業も遵守しなければならない会計処理の規範
- 企業会計基準は、慣習法(慣習にもとづいて成立する法)の性格を有する。
- 1949年公表の企業会計原則(企業会計基準のひとつ)
「企業会計の実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約したものであって、必ずしも法令によって強制されないでも、すべての企業がその会計を処理するに当って従わなければならない基準」 - 企業会計における実践規範として機能している。
- 1949年公表の企業会計原則(企業会計基準のひとつ)
企業会計基準の設定機関の変遷
- 企業会計基準委員会
- 企業会計基準を設定している民間機関
- 「財団法人財務会計基準機構」の傘下に置かれ、新規に公表される会計基準の設定を担っている。
- 民間企業からの会費収入によって運営され、専従の職員や研究員を有している。
- 民間の機関が企業会計基準を設定しはじめたのは最近のこと。
- 2001年7月
- 財団法人財務会計基準機構の設立
- 2002年2月
- 企業会計基準第1号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」が公表された。
- 2001年以前
- 基準設定は大蔵大臣の諮問機関(しもんきかん)である大蔵省企業会計審議会が担っていた。
- 企業会計審議会は、現在においても金融庁長官の諮問機関として存続しているが、実質的な会計基準設定の役割は民間の機関に委譲された。
- 2001年7月
- 国際的な潮流のなか、日本における会計基準の設定主体も官から民へと移された。
- アメリカの体制
- 財務会計審議会(Financial Accounting Standards Board [FASB])という民間の機関が会計基準の制定を担ってきた。
- 国際会計基準審議会(International Accounting Standards Board [IASB])も同様に非政府機関として存在している。
- アメリカの体制